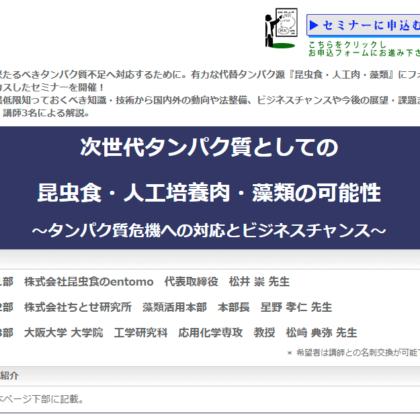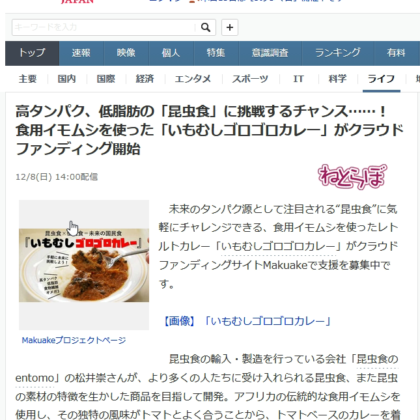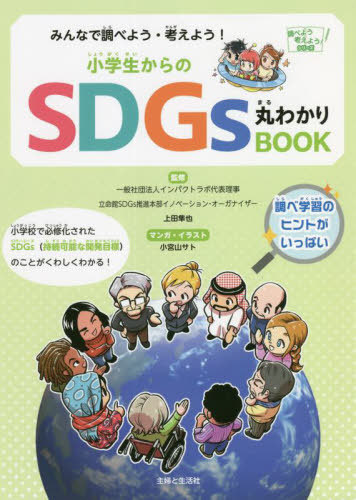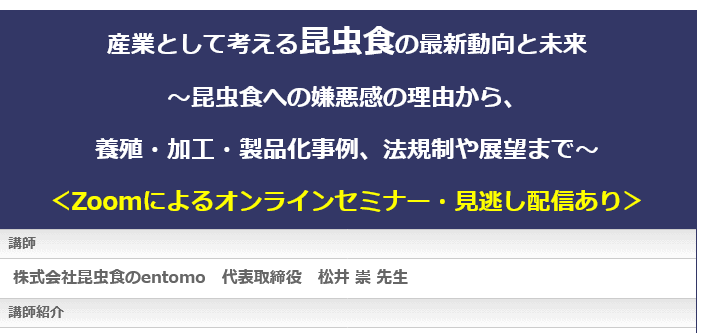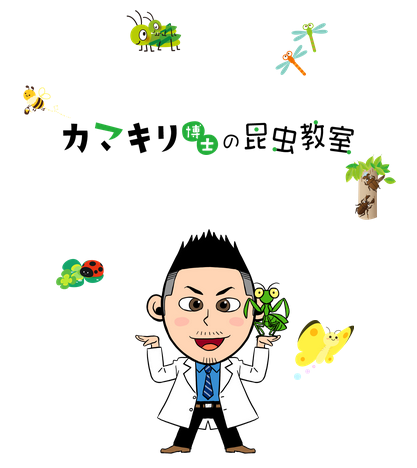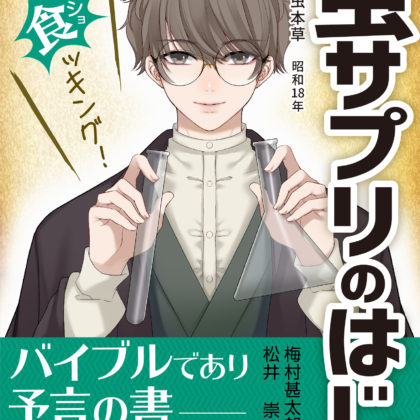昆虫食が文化として普及するためには
昆虫食が文化として普及するには、
①食用昆虫の安定供給
②昆虫の見た目のハードルを下げる
③昆虫の安全な食べ方の普及
④レシピ開発
⑤製品開発
⑥料理人育成
が必要ではないでしょうか。
①食用昆虫の安定供給
牛や豚、鶏、魚、野菜はどこのスーパーで販売されており、誰でも購入することができ、供給量も豊富です。一方、容易に入手できない食材は、たとえ栄養価が高くて美味しくても、広く普及することは難しいです。これは食用昆虫にも言えることです。
現在、安定供給可能な食用昆虫の種類は非常に限られています。食用コオロギの養殖が欧米やアジアなど世界中で盛んな理由は、コオロギは雑食で乾燥飼料で育ち、大量養殖が容易だからです。下記はカナダの食用コオロギ養殖企業Entomo Farmsの工場の外観と内部です。



②昆虫の見た目のハードルを下げる
他の食材も、見た目や盛り付けを工夫しています。昆虫は文化的背景もあり、他の食材以上に見た目を気にする必要があるかと思います。
③昆虫の安全な食べ方の普及
昆虫も他の食材と同様、生食は危険です。また昆虫の調理方法や加工方法に問題がある場合は、他の食材と同様に、不味かったり異臭がする場合があります。
④レシピ開発
肉や魚、野菜の調理方法やレシピ、料理本は多数存在しています。例えば食材をスーパーで購入して、家で料理本を参考にして調理し、美味しく食べることができます。
しかし食用昆虫には、他の食材のような調理方法が確立されておらず、レシピや料理本はありません。そのため、たとえ昆虫食に興味があったとしても、昆虫の調理方法が分からないため、食べ方が分からず、美味しく食べることができません。
そのため、他の食材同様に、レシピ開発とレシピの普及が必要不可欠です。私達が毎月なんば赤狼で開催している試食会イベントでは、食用昆虫を使ったレシピ開発を行っています。レシピは順次、ブログで公開する予定です。
画像は第3回昆虫食試食会イベントで提供したハンバーガーとブラウニーです。ハンバーガーのパンにクリケットパウダー(粉末コオロギを使用。ハンバーグにミールワームを使用)


⑤製品開発
プロテインバーのように、既に製品化されたものであれば、昆虫の調理方法が分からなくても、昆虫を美味しく食べることができます。

⑥料理人育成
他の食材と同様に、昆虫の特性を活かした調理方法を開発する料理人の方が、一人でも増えることが必要です。